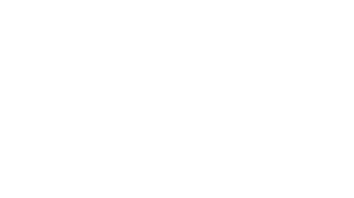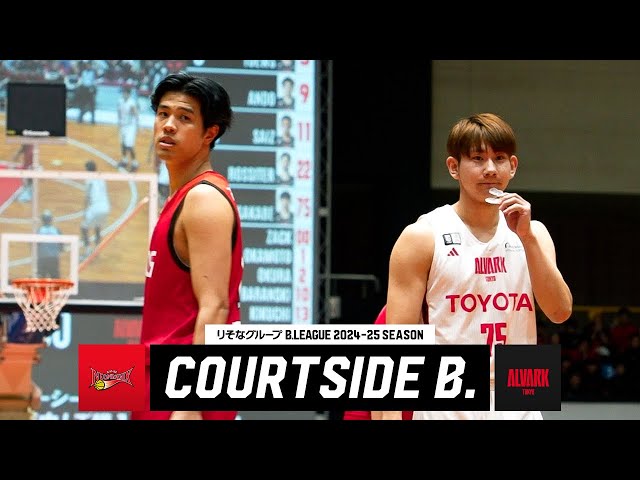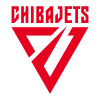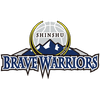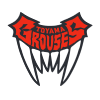第5回 B.LEAGUE×まちづくり委員会~『非日常』から『日常』へ、地域創生を目指すBリーグの『まちづくり』の形
2025年3月24日、まちづくり委員会の第5回では、過去4回で行われてきた事例紹介と討議の内容がまとめられました。
日本の各地域で少子化や人口流出が進む状況に対して、Bリーグとしては地域を活性化して人口流出を止め、人口を増やし、雇用が生まれ、企業が増えていくような循環がないと、Bクラブを応援してくれるファンや企業が減ることになります。
Bクラブの事業の持続的成長は地域あってこそ成立するものである以上、従来のスポーツビジネスの枠を超えて、『非日常から日常へ』というチャレンジとして、Bリーグ、Bクラブはまちづくりに取り組みます。
バスケットボールには、若者、女性、ファミリー層に支持され、さらにはバスケットボール自体がストリートや音楽など様々な若者文化と融合した競技という特徴があります。また、Bクラブの本拠地となるアリーナは、コンサートやMICEなどバスケ以外にも多様なイベントを実施でき、コンパクトな敷地で市街地にも建設できるという特徴を持ち、若者やファミリー層にも求心力のある市街地拠点としての可能性があります。
現在の日本が人口減少、超高齢化社会、格差社会に直面する中で、本委員会でとらえたまちづくりの方向性は「居心地が良く、歩きたくなるまちなか」であり、重要なキーワードを「コンパクト+ネットワーク」、「ヒト中心ウォーカブル」、「ダイバーシティ」、「公民連携のスパイラル」にまとめました。
試合とそれに伴うイベントは『非日常』ですが、そこから『日常』へと踏み込んで、アリーナでマルシェを開催したりコワーキングスペースやイベントや会議スペースとして活用したり、部活動の地域移行などスポーツを楽しむ交流拠点を設けることで子供たちとその親が集まる場になります。そこで新しい会話が生まれ、出会いが始まります。こうして『日常』にも人が集まり、市街地の賑わいも生まれます。
これを実現するためにまず必要なのは、Bクラブが主体性を持つこと。まちづくりに対する思いを持ち、様々なステークホルダーと議論を重ねる中で共通のビジョンへと仕立て上げ、「本当にこれが人々に喜ばれるのか」、「人が来てくれるのか」、「事業として回るのか」を検証しながら本格的なフェイズへと進めていく。これらをBクラブが主体性を持って進めていくことが重要です。
そんなBクラブのまちづくりを、Bリーグは広報活動、座組構築、人材獲得といった面で後方支援していきます。リーグが描く感動立国と、それに繋がるまちづくりのイメージが、この委員会でより具体化され、今後の指針が示されました。
過去の記事はこちら
第4回 B.LEAGUE×まちづくり委員会~琉球ゴールデンキングスとベルテックス静岡、佐賀県による事例紹介~
第3回 B.LEAGUE×まちづくり委員会~川崎ブレイブサンダースと東洋大学大学院が事例紹介~
第2回 B.LEAGUE×まちづくり委員会~長野市とシーホース三河、MINTO機構が事例紹介~
第1回B.LEAGUE×まちづくり委員会が開催!~茨城ロボッツと秋田ノーザンハピネッツが事例紹介~