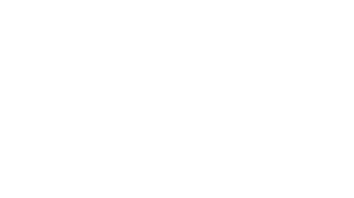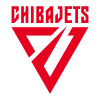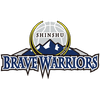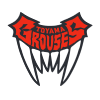第3回 B.LEAGUE×まちづくり委員会~川崎ブレイブサンダースと東洋大学大学院が事例紹介~
今、日本各地に『夢のアリーナ』が次々と誕生しようとしていますが、議論はなされているものの具体的な形は見えていません。「B.LEAGUEのクラブがあり、そこにアリーナができることで街をどう変えていけるのか」をテーマに、スポーツがまちづくりに果たす役割を整理し、可能性を示すだけに留まらず、どう実行していくのか、どう継続させていくのかを明確にしていくことを目的に組成された「B.LEAGUE×まちづくり委員会」の第3回が開催されました。
1月27日に行われた第3回では、「社会課題解決×スポーツまちづくりとは」をテーマに、川崎ブレイブサンダース、東洋大学大学院 による事例紹介と、それに対する討議が行われました。
「川崎からバスケの未来を」人と街を元気にする川崎ブレイブサンダースの取組み
川崎市は、政令市の中で最も平均年齢が若く出生率も高い街です。また、歴史的に挑戦を続けて成長しており、若者文化に対する理解の高い街でもあります。その川崎市で、市と連携したまちづくりを進めているのが川崎ブレイブサンダースです。
川崎ブレイブサンダースの親会社であるDeNAのグループ会社には、横浜DeNAベイスターズ、SC相模原など複数のスポーツクラブがあります。DeNAグループがスポーツ領域で掲げるミッションは「スポーツの力で”ひと”と”まち”を元気にする」。「ひと」だけでなく「まち」も入っているのがポイントで、IPコンテンツ(球団・クラブ)、スタジアム・アリーナ、隣接街区・周辺街区のまちづくりを一体として各地域で事業を進めています。
川崎ブレイブサンダースでは2018年に「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL 川崎からバスケの未来を」というミッションを策定し、まちづくりに関わる事業を積極的に行ってきました。
川崎市から事業者に選定されて運営する若者文化発信拠点「カワサキ文化会館」は、開業から2年弱で約5万人が利用。バスケットボールやスケートボード、ダンスなどの体験・交流ができる施設で、施設内のカフェでは、 である味の素(株)と連携したアスリート向けの補食の販売も行っています。現在の「カワサキ文化会館」は年内に営業終了予定ですが、市からこれまでの活動が認められ、後継施設を作ることが決定しました。
武蔵小杉駅の高架下に”こどもの第3の居場所”として設置した「THE LIGHT HOUSE」は、高校生以下は無料で利用できる施設。バスケだけでなく、トランプをしたり漫画を読んだり宿題をしたりして、家に帰るまでの時間を過ごせる場所となっています。こどもたちを取り巻く「孤食」や「関係性の貧困」を少しでも解消するため、月に1回こども食堂も実施しています。
JR川崎駅北口に位置する「THE KAWASAKI VISION」は、川崎市が保有している場所にスポンサーと連携して大型LEDビジョンを2基設置し、広告媒体として運用しています。
LEDビジョンではクラブ自身の広告と外部に販売した広告、川崎市の情報を発信。新アリーナの玄関口となるこの場所をしっかり媒体として価値あるものにすること、その上で広告事業として収益化することを目指しています。
こうした事業の経験も踏まえて、親会社のDeNAとともに「川崎新!アリーナシティ・プロジェクト」として川崎市・京急電鉄と連携した新アリーナを含む複合エンターテインメント施設の建設計画を進めています。
このプロジェクトでは、アリーナだけでなくアリーナシティとして周辺地域も開発するために、クラブの範疇を超えたところも市と連携して推進しています。例えば、アリーナへ向かう市道ににぎわい を創出するため、キッチンカーや休憩スペースを設置する実証実験にDeNA、川崎市とともに取り組んでいます。また、アリーナ予定地のすぐ東を流れる多摩川の活用についても検討しており、昨年11月には音楽やバスケ、ダンスなどのストリートカルチャーで盛り上げるイベントを開催しました。
クラブがまちづくりに取り組む意義について、代表取締役社長の川崎渉氏は、「クラブは民間企業であり、理念だけでは続かない。理念以外にも中長期の取り組みの意義を持つことが大前提」と話します。短期的な経済合理性、あるいは中長期的なブランディングやマーケット拡大といった何らかの意義に当てはまることが必要ということです。
また、行政との連携における役割分担ついて「民間が取れるリスクは民間で取るべきであり、民間では踏み切れない投資へのサポートや民間ではできないルールメイクを行政に期待している」「行政がまちづくりの絵を描いてくれることを期待するのではなく、こちらで絵を描いて、賛同して巻き込んでもらうことが大事」ともいいます。
クラブが描いた絵に賛同してもらえるのは、その絵が街にとってポジティブであったり、行政が弱い部分を補うことができるものであるからこそ。「アリーナの完成はゴールではない。開業したアリーナで何が行われるか、川崎が世界に誇れる街になるかどうかこそが大事」という川崎代表。クラブと行政が互いの強みを持ち寄り、補完し合いながらの挑戦は続きます。
「スポーツアリーナにおけるPPP」東洋大学大学院
公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームをPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ:公民連携)と呼びます。PFI(プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ)は、PPPの代表的な手法の一つで、公共施設の設計・建設・維持管理・運営に民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方です。
東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻の中村郁博教授は、いま、新しい形のPPPが求められているといいます。これまでのPPPは、PFIや指定管理など、政府セクターと市場セクターが中心となった、いわば狭義のPPPでした。いま、地域セクターが関わる「新しい公共」ともいうべき地域ビジネス型のPPPの重要性が増しているのです。
最先端のPPPとして中村教授から共有されたのが、大阪市の都市計画公園に作られた「汐かけ横丁」という屋台村の事例です。
スモールビジネスのインキュベーション機能も持つこの屋台村は、地域の人が飲食店を始める際には初期費用なしの賃料だけで出店ができ、備品等は全て借りることができます。
ポイントは、賃料が周辺の物件より高く設定されていること。開業時に資金がない事業者も、事業展開し成功すれば顧客がついている状態になります。そうなれば屋台村から周辺の家賃の安い店舗への移転が促されるので、地域が活性化するという仕組みです。
このようなPPPは、今までのようなPFIとは毛色が違うが、地域を活性化させ地域の人々に幸せを与えるものです。そして、こういう発想は行政ではなく民間が得意とするものだといいます。
アリーナの特徴は、経済的利益と社会的便益の両方を追求できることです。スポーツには経済的利益だけでなく、人が集まる、観た人が楽しいと思う、健康を増進するといった社会的便益があります。まちづくりや地域活性化の中核となることが可能であり、地域の自立の促進や住民のシビックプライドの形成にも繋がります。
一方で、アリーナが利益と便益を確保するためには、継続的な運営における工夫が必要であり、また、専門性が必要とされます。そこで、従前のPPPの「リスク分担」の考え方から、「リスク管理」の考え方に移行する必要が生じます。
また、PPPによるアリーナの整備においては、地域住民を巻き込んで地域住民からの支持を得ることが何よりも重要です。アリーナは行政が公共サービスとして必ず提供しなければならないものではありません。しかし、社会的便益や経済効果が大きいから、行政が整備しようとしている。そこで何が正しいかを決めるのは、地域住民です。
PPPにおいては画一的な理想形があるわけではありません。例えばアリーナの意味も、製造業のまちで財政は豊かだがシビックプライドの不足する地域なのか、雪国で冬場に運動ができる場所がない地域なのか、地域の実情によって大きく変わります。1つ1つをケースバイケースで作る必要があるのです。
中村教授は、PPPの新しいあり方として大きく二つの可能性を提言しています。
一つが、あらかじめ事業の公共性と効率性を契約等により担保する事業体である「PPPプロジェクト」から、主体的に意思決定し事業計画や戦略を変更することができる「PPPエンティティ」への移行です。
二つめは、PPPに、クラブ等の民間事業者である「PPPプレーヤー」に加えて、政府から権限の委譲を受けPPPプロジェクトを企画・実行する「PPPエージェント」、PPPプロジェクトの成功に向け事業戦略を立案し手続きを適正に進捗させていく「PPPプロデューサー」が関わることです。
これらにより、機動性、柔軟性、発展性が確保され能動的なリスク管理ができるとともに、専門性への対応が可能になり、多様で複雑なニーズに対応できるPPPの実現が期待できることになります。
中村教授は、「経済を動かすことと社会的便益をつなぐことができるのがスポーツの特徴であり、新しいPPPはまさにそういうことにチャレンジしていかないといけない」と、地域においてクラブとアリーナが果たす役割に期待を寄せました。